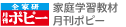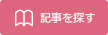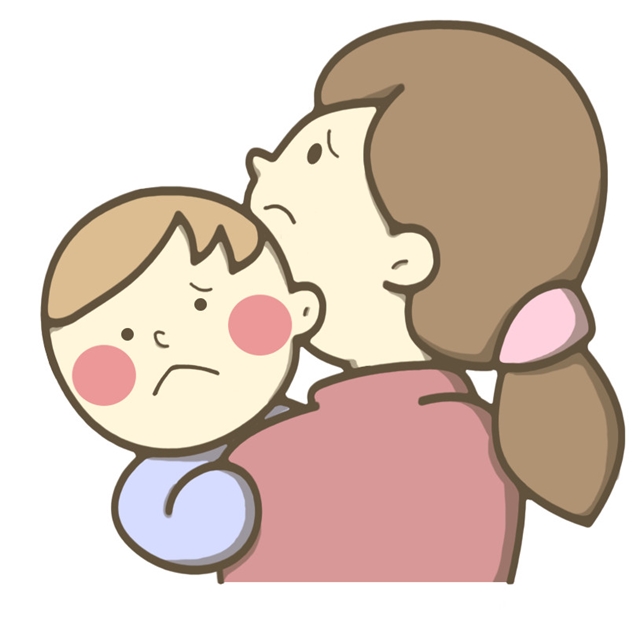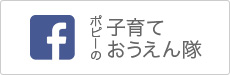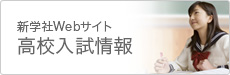ヒゲおやじ先生の脳コラム
読書と成績の関係は?
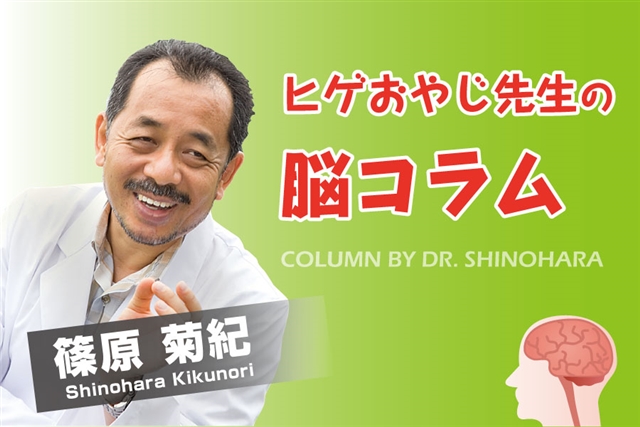
今回は読書に関するお話です。読書習慣がつけば成績が上がるというシンプルなことではないようですが、やはり読書は大事だと再認識できますよ。
読書は大事と思わせる研究
ペンシルベニア大学のローソン氏らは、同じような生活レベルの家庭で育った64人の子どもを対象に、4歳のとき、8歳のとき、18・19歳になったときに彼らの認知機能調査や脳スキャンを行いました。
その結果、4歳のときに本や知育玩具を与えられ、動物園や遊園地などへ連れて行かれた子どもたちは、そういうことをされていない子どもたちに比べて、とくに言語テストの得点が高く、左脳の発達が優れていたそうです。また、このような介入を8歳で行っても、効果はなかったそうです。
幼児期からの読書や体験は大事、と思わせる研究です。
読書で学力は向上するか
ベネッセ教育総合研究所の木村先生らは、電子書籍の利用状況と成績の変化を報告しています。2016年8月と翌年12月の2回の学力テストを受けた小学5年生42,696名について、その間の電子書籍利用量と学力テストの成績変化を調べたのです。
電子書籍利用が読書のすべてを示すわけではありませんが、この調査の結果、電子書籍の利用「なし」、1~2冊の「少」、3~9冊の「中」、10冊以上の「多」に分けると、「なし」は成績(平均50点、標準偏差10として)が0.7点下がり、「少」で0.9点、「多」で1.9点上がったそうです。
読書はやはり成績向上に関わるようです。
成績下位群ほど関連が強い
読書で知識が増えたから成績が向上したのではなく、読書の習慣により生活が落ち着き、学習しやすい心構えや環境が整ったことが大きいのではないか。だから、もともと学習習慣のある成績上位群より、あまり学習習慣のない成績下位群で効果が大きくなったのではないかというのです。興味深いことに、この研究で最も読書効果が大きかったのが、「国語」ではなく「算数」だったそうで、この点からも、読書そのものより学習習慣と読書の関連が学業成績に寄与したことを示唆するのではないかとのことです。
他の要因の関わりは
ひと昔前なら、ここで話を終えることができました。しかし研究が進み、学業成績には社会経済的要因(親の年収、学歴など)や遺伝的要因が関わることが指摘されるようになってきました。
今回紹介した研究は、どちらも同じ子どもを追跡した調査なので、社会経済的要因や遺伝的要因の多くは、調査時点間に変化がなければ除去できていると考えられます。それでも「一般知能などは遺伝的要因が学年を増すにつれ大きくなる」とか「読書や動物園へ連れて行くなどの望ましいことを親がしたがる傾向にも遺伝的要因があるのではないか」といった仮定を持ち込むと、こうした研究の結果も限定的に捉えておく必要が出てきます。親が望ましいことをしたがる傾向と一般知能が相関し、そういう家庭が望ましいことをしたがり、かつその子は後伸びする、というのです。
それでも読書はおすすめ
最新の記事一覧
2023.03.10
2023.03.10
2023.03.10
2023.01.13
2022.11.14